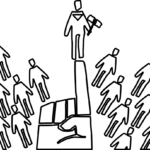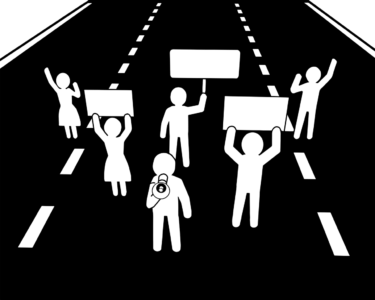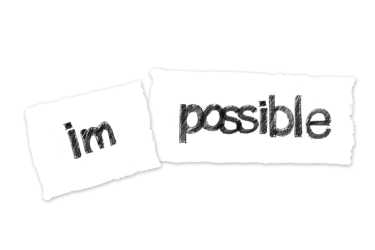アンダーマイニング効果の意味
アンダーマイニング効果とは外的報酬が与えられることによって人間の内発的モチベーションが低下する現象のことです。人間のモチベーションには「好きだからやる」などの内発的モチベーションと「先生が怖いから勉強する」「お金のために働く」などの外発的モチベーションがあります。アンダーマイニング効果が起きると、この二種類のモチベーションが入れ替わってしまうことがあります。具体的な例をあげると、お手伝いとしてお皿洗いしている子供がいたとします。最初のモチベーションは好奇心や大人の真似をしたいという自分自身の中にある内発的なモチベーションです。ここで親がご褒美として100円のお小遣いを渡したとします。するとだんだん子供はお小遣いをもらうために、外発的モチベーションに基づいてお手伝いをするようになります。最終的に、もともと持っていた内発的モチベーションが低下し、お小遣い無しではお手伝いをしなくなってしまいます。このような現象が典型的なアンダーマイニング効果です。
アンダーマイニング効果の原因
アンダーマイニング効果を引き起こす一番の原因は「自分の行動は自分で決めたい」という自己決定への欲求です。人間は「やりたい」と思っている行動に対しては内発的モチベーションが向上しますが、「やらされている」と感じる行動には内発的モチベーションが低下します。この理由は「やらされている」状態では自己決定への欲求を満たすことができないためです。同じような現象が人間に報酬を与えた時にも発生します。報酬が与えられたとき人間は「報酬によって自分の行動がコントロールされている」と感じることがあります。この状態では自己決定への欲求が満たせず、結果的に内発的モチベーションが低下するのです。お手伝いをする子供の例でいうと、お小遣いを渡されたことにより、お手伝いを「やりたい」から「やらされている」と認識するようになります。やらされているお手伝いでは自分の意志で行動していると感じることが出来ないので、自主的にお手伝いをする気がなくなるのです。
あとがき
アンダーマイニング効果は定義だけ見ると「報酬によってモチベーションが低下する」という怖い現象です。しかし、原因を理解するとこの現象が起きる状況は限定的で、対策可能であることが分かります。結局は報酬を受け取った人間が報酬に対してどのように認識するかという問題なので、本人に自分の力で報酬を手に入れたと認識させれば自己決定の欲求は満たされ、内発的モチベーションも維持されます。外的報酬自体は悪いものではなく、内発的モチベーションに比べてコントロール可能であることなどメリットもあるため、アンダーマイニング効果を考慮しつつ利用していくべきでしょう。
.
関連記事:
動機付け理論
.
リーダーシップ論の記事一覧はコチラ
スポンサードリンク